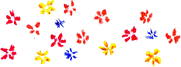昔から私はどんくさい子どもであった。
道を歩けば小石や空き缶やらなんやらに躓き、たとえ何も落ちてなくとも蹴躓いた。
溝があれば嵌まるのはしょっちゅうだし、認識していても人や車を避けようとしてずぼりと嵌まってしまう。
体育で球技をすれば顔面にボールを受けるのはよくあることだし、ハードルをもれなく倒してしまうなんて当たり前。
あ、でも水泳と短距離は普通にできる。
水泳はトラブルになる要素が少ないし短距離は短い分転ける可能性も低いから。
両親は私のあまりにもどんくささに呪われてるんじゃないかと半ば本気で思ったらしくお祓いにも連れていかれた。
が、もちろん効果はなく両親もこれは天性のものだと諦めたのであった。
とりあえず命に関わるようなヘマはやらかしたことがなかったのでそこまで神経質にならなくていいとの見解を出したようだ。
私自身もなるだけ気をつけつつそれでもやっぱり細かいドジをしてしまいながらもなんとか高校に入学することができた。
新しい学校生活は何もかもが新鮮で期待と不安が入り混じってふわふわした気分にさせた。
入学して半ば、少しずつだけれどクラスにも馴染みはじめてきた頃のこと。
今日は教室の掃除当番だったのでグループの皆でちゃちゃっと終わらせて、
最後にじゃんけんで負けてしまった私がゴミ捨てに行く羽目になってしまった。
ついてないなぁ。
そう思いつつ1日分たっぷりゴミを溜め込んだゴミ袋を両手に担いで焼却炉に持っていく。
早く終わらせて部活に行かないと。
そればかりが頭を締めていたせいか、私はまたも足を躓かせ見事にすっ転んでしまった。
校舎の裏手、でこぼこも石ころも特に何もない普通の地面で転んでしまったのである。
なぜ何もない所で躓くのか。本当にどんくさいとしか言いようがない。
ほとほと呆れながらじんじんと痛む足を見やる。
痛いと思ったらやっぱり派手に膝を擦りむいてた。
じゅくじゅくとした傷口からは血が滲み出ている。
おまけにふと向けた視線の先には転んだ際に放り出してしまった
ゴミ袋が力なく転がっており放った際に破けたのか中のゴミが周囲に散らばっていた。
その光景に自然とため息が出てきた。
足は痛いしゴミは散らばるし散々だ。
そう気分が落ちてくると次第に涙腺が緩んできた。
ここで泣いてしまっては情けなすぎてどうしようもなくなると必死に堪えていると、後ろの方からじゃりっと地面を踏みしめる音がした。
はっとして咄嗟に振り返ってから後悔する。
今の私は膝小僧を派手に擦りむきゴミの散乱する場所でいい歳して半泣きになっている女なのだ。
やばいと思いつつももう遅い。
視線の先には頭を坊主にした恐らく先輩であろう人がこちらを見てぎょっと固まっていた。
手にはゴミ袋が握られていて私と同じゴミ捨て当番なのだろう。
その人は散らばったゴミを見て、私の顔と足あたりをざっと見渡して理解したという風に頷くと
「ちょっと待ってろ!」と言ってからゴミの傍に駆け寄りなんと拾い始めたのだ。
「あ、あ、私やりますから!どうかおかまいなく!」
「いーから、じっとしとけって。」
先輩が持っていた袋を開けて私のクラスのゴミを入れる。
私があわあわと混乱している間に素早く片付けて最後に袋の口をぎゅっと結ぶと
また私に待っていろと命じるとさーっと焼却炉の方へと駆けていく。
ぽかんと半ば呆然としたまま待っていると程なくして先輩が戻ってきた。
「すみません!ほんとありがとうございました。助かりました!」
「いいって、ほらそれよかこれで足拭け。」
先輩はいつの間にか濡らしたタオルを持っていて、それをこちらに押しつける。
「大丈夫ですよ!タオル汚れますから!」
「そんな血ダラダラじゃ歩けねえだろ。んなこと気にすんな。」
ぐいっと手に握らされたタオルにまたありがとうございますとお礼を言ってから血や土で汚れた足を拭った。
「じゃあそのままタオル傷口の所で縛っとけよ。―よし、んじゃ保健室行くぞ。」
「いえ、一人で行けますから……いだっ!」
保健室まで連れていってくれそうな先輩を制して立ち上がった瞬間左足に鈍い痛みが走った。
思わず足を押さえて踞っていると先輩が同じように屈みこむ。
「あー、足捻ってるかもな。」
「いたたた…」
「…しゃあねえ。ほれ。」
くるりと反転して背負う体制になった先輩に意味が分からずきょとんとしていると先輩が早く乗れよと急かしてきた。
―ん?乗れとな?
「まさかおんぶで運んでくれるってことですか!?」
「みなまで言うなよ。歩けねえだろそのままじゃ。」
「大丈夫ですよ!本当に!ほら私重いですし!」
ぶんぶんと手を振って拒否するが、何よりそんな恥ずかしいことできない。
先輩は恥ずかしくないのだろうか。
いや、たぶん親切心だけで言ってくれてるのだろうけども!
「これでも運動部で鍛えてんだぞ。大丈夫だから早くしろって。」
有無を言わさない先輩の眼力に負けて、失礼しますと一言断ってからその背中におぶさる。
よっと声を上げて立ち上がり歩き始め、「なんだ全然軽いじゃん、ちゃんと飯食ってんのか」と謎の心配をされた。
かろうじて食べてますよと返事をしたが、やはりこの体勢は恥ずかしい。
なるべく俯いて周りに顔を見られないようにし、
せっかく運んでくれている先輩には申し訳ないけれど早く着いてくれと切実に願った。
「お!龍ー!何やってんだー!!」
そんな居心地の悪い空気の中、唐突に明るい大きな声が聞こえて思わず顔を上げた。
前方に恐らく先輩の知り合いと思われる背の低い人と穏やかそうな男の人がこちらに向かって歩いてきた。
ただでさえ恥ずかしいから人に会いたくないのに先輩の知り合いとか…!
気づかれた以上上げていた顔を逸らすのも失礼かと思い、気合いで羞恥心を押し留める。
「おー!ノヤっさんに縁下!」
「どうしたのその子?」
「ちょっと怪我したみたいでな、足捻ってるし保健室連れて行く所だ。」
「そうだったか!さすが龍!男だな!」
どっちがノヤっさん?で縁下さんか分からないけれど
小さい人がビシッと親指を立てて褒めたのに対し先輩もよせやい!と照れている。
なんだか仲が良さそうだ。
「というわけだから大地さんにちょっと部活遅れますって言っといてくれるか?」
「ああ、わかったよ。」
「え、あ…ごめんなさい!私ここから一人で行けますので!どうぞ部活の方へ行ってください。」
「何言ってんだよ。さっきすげえ痛そうにしてただろ。」
「でも私のせいで部活に遅れますし……」
「んなこと気にすんな。そのために伝言頼んでんだしよ。」
「いいからいいから。こいつのこと使ってやってよ。顔は厳ついけど悪いやつじゃないんだ。」
「一言余計だ縁下!!」
先輩の友人の方々にも背中を押されて申し訳なさに頭が下がった。ほんといい人だな。
「すみません、お願いします。」
「―おお。」
おずおずと言葉を口にすれば先輩は力強く返事をしてくれた。
二人にも会釈してその場を離れた。
目的地の保健室はすぐ近くまで来ていたのでそれからあっという間に着いた。
扉の前で下ろしてもらい、慎重に床に足をつける。
「ここまでで大丈夫です。」
「おう。平気か?」
「はい。」
なんだか地に足をつけるのがとても久しぶりのように感じる。
実際はそんなに経ってないんだろうけど。
「じゃ、ちゃんと足診てもらえよ。」
「あ、待ってください!」
保健室に着いたらさっさと踵を返す先輩を慌てて呼び止めた。
「あの、本当にありがとうございました!」
がばっと若干勢いが良すぎるほど頭を下げる。
ここまでしてくれて本当にとてもありがたかったのだ。
感謝の気持ちが少しでも伝わればとドキドキしながらそっと頭を上げて先輩の様子を窺う。
「……次からはちゃんと転ばねぇように気をつけろよ。」
少し照れたようにだけどにっと笑った先輩の顔にまたどきりと胸が跳ねた。
じゃあな!と颯爽と去っていく先輩の背中をぼんやりと見送りながら
今度は足じゃなくて心臓が痛くなってきたようだ。
傷口に生クリーム
title by alkalism
2014.10.13